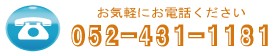防火設備定期検査業務基準 (テキスト抜粋)
1.定期検査制度の趣旨
建築物に期待され、要求されている諸性能を維持保全することは、本来は建築物の所有者、管理者又は占有者がそれぞれの責任によってなすべきものであり、建基法第8条においても所有者等に、建築物を常時適法な状態に維持するよう努力義務が課せられている。
しかし、公共性のある建築物や第三者が多数利用する建築物等の場合には、所有者等により維持保全の不備・不具合によって事故や災害が発生したり、また被害が拡大したりして、第三者に危害を及ぼす恐れがあることから、建基法第12条第1項及び第3項では、所有者(管理者)は、その建築物等について、定期にその状況を資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けている。
なお、調査・検査報告を受けた特定行政庁は、その報告内容に応じて措置を講じることとなる。
また、国等の管理する公共建築物及び公共建築物に設置する防火設備・昇降機・建築設備については、建基法第12条第2項及び同第4項により点検義務が課せられている。
2.定期検査の基本事項
2.1 事前準備
(1) 感知器を作動させ、防火扉、防火シャッター等の閉鎖を確認するため、事前に、連動制御器の起動、復旧等の事項について所有者等と打合せを行うこと。また所有者等の現場立会を要請すること。
(2) 検査内容、検査に要する時間及び検査に必要な人員は、他法令による検査記録(3.1 書類審査(2)参照のこと。)の有無により異なるので、あらかじめ建築物所有者等と事前打合せを行う。
(3) 検査に当たっては、必要に応じて防火設備検査員が指定した者を補助検査員として検査の補助を行わせることができる。
(4) 検査に際しては、あらかじめ前回の定期検査報告書(初回の検査の場合は完了検査記録等とする。)の内容、防火設備に係る不具合の状況、検査結果の特記事項、改善事項の有無等を確認する。
(5) 消防法令に基づく自動火災報知設備の点検など、関連する検査業務との連携(同一日に検査を実施する機会を提供するなど)を図り、建築物所有者・管理者の負担を軽減するように努めること。
2.2 検査関係
(1) 随時閉鎖式の防火設備の全数検査を実施すること。
(2) 検査終了後、検査が捜査した電源スイッチ及び各種スイッチ及びスイッチ類等は定位置に必ず戻し、機能が十分発揮できるようにしておくこと。また、最初の状態を記録し、検査終了後に記録と合わせて確認すること。なお、その際には所有者等の確認を得ること。
(3) 法第68条の26第1項の規定による国土交通大臣の認定を受けた随時作動式の防火設備等も定期検査の対象となる。認定を受けた機器・装置等の検査は、認定取得時の検査方法を記載した図書も踏まえて検査を実施する。
3.定期検査の要領
3.1 書類審査
(1)建築完成図書
検査に先立って、当該建築物に備えておくべき関係図書(確認済証、検査済証、建築確認図書など。)の有無を確認すると共に閲覧する。
①当該検知器確認図書(確認済証、検査済証、建築確認図書など。)の内容を確認し、建築物の構造、規模、避難経路等を把握する。
②増築、改築、用途変更等の有無を確認する。
③建築確認図書により、防火設備の概要(防火扉及び防火シャッター等の位置、感知器及び連動制御器の位置、手動開放装置の位置、中央管理室の位置など。)を確認する。
④感知器が連動機構用または自動火災報知機併用であるか、防火設備の設備図面により確認する。
⑤建築物の保守管理日誌等を閲覧し、建築物の保守管理の状況を把握する。
⑥既存不適格の判断を的確に行うため、確認済証及び検査済証の交付年月日等を確認する。
(2)定期検査記録等
①前回の定期検査報告書の有無を確認する。
②前回の定期検査報告書に記載された指摘の内容、指摘の概要、改善予定の有無及びその他特記事項の記載内容を確認する。
③前回の検査以降に、消防法令による検査記録又は自主検査記録(以下「既住記録」という。)がある場合は、実施時期、検査方法等が適正であるか否かを確認し、適正と判断できる場合は検査記録とすることができる。
この場合において、防火設備検査員は、既住記録の内容が防火設備検査業務基準に適合しているかどうかを確認し、不足する事項があれば、当該事項に相当する追加の検査を行わなければならない。
なお、検査記録は、直近に実施したものを使用し、消防法令による検査記録にあっては3ヶ月以内のもの、また自主検査記録にあっては1ヶ月以内のものとする。
3.2 保守管理の状況
保守管理がどのように行われているかを所有者等から聴取するとともにm保守管理に関する記録(防火設備に関する保守管理日誌など。)を閲覧する。
また、全検査終了後に防火設備に関する保守管理の状態を所有者等にほうこくし、改善内容等を指導する。さらに総合的な維持保全計画書が策定されているか否かを確認し、策定されていない場合は、当該建築物の規模、用途等を勘案して、策定するように指導する。
特に防火設備は火災という非常時に機能するものであることから、これに即応できる保守管理業体制が確立されていなければならない。この点について所有者等に対して十分説明し、適切な保守管理体制のあり方を指導する。
4.定期検査の手順
検査は、国土交通省告示により規定される検査項目、検査事項、検査方法及び判定基準に基づき検査する。検査にあたっては、特に次の点に留意する。
(1)書類審査により検査対象物の設置状況を確認する。
(2)はじめに検査対象物全般について外観検査を行い、完成図書のとおりに検査対象物が設置されているか確認する。
(3)特に防火シャッター、耐火クロススクリーン及びドレンチャーその他水幕を形成する防火設備の防火区画の構成範囲を確認する。
(4)検査対象の防火設備を中央管理室から遠隔操作を行う場合は、非常放送設備等を活用うえ安全に留意し実施する。
(5)中央管理室等から遠隔操作を行う場合は、当該建物の防火管理者等の立会いにもとに点検を実施する。
(6)居住者や在館者等に混乱が起こらないよう、事前に管理者・所有者等から検査日時等を周知するよう要請する。
(7)検査終了後、すべてが元の状態に復旧されているかを確認する。またその旨を所有者等に報告する。